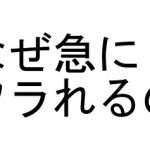群ようこ、という作者名はどこで知ったんだろうとふと考えてみるが思いだせない。国語の教科書で見たのかもしれないし、姉の本棚で見たのかもしれない。手持ちの本がなくなり、周りの隊員から借りた本で久しぶりに群ようこの作品に触れた。
ちなみに文庫のカバーには
「アメリカに行けば何かがある」と夢と貯金のすべてを賭けて一人渡米した群さんの愉快なアメリカ観察記
と書かれている。この本は1987年刊行の「アメリカ恥かき一人旅」を書名変更し文庫化したものとなっており、あとがきには本の刊行まで3年かかったとなっているため舞台は1980年代初頭ということなのであろう。ちょうど私が生まれたころということでもう30年以上も昔の話である。
大卒初任給が12万程、1ドル230円の時代のため20歳の著者(大学生)が海外に行くというのはとてもハードルが高かったのではないかと思う。そうした時代であれば「アメリカに行けば何かがある」と夢見るのも不思議ではないかもしれない。本書はこれらアメリカへの渡米経験を基にしたエッセイである。
日本人だというのに入国審査で怪しまれ危うく強制送還か、というのっけからの展開をみてもさすがに時代を感じずにはいられないが、この本を読んで感じたのは今の自分の状況にどこか似ている、ということであった。現代のように国際化社会でない30年前のアメリカは現在のアフリカとどこか同じような雰囲気を醸し出している。アメリカを一文字変えて「アフリカ居すわり一人旅」とし、舞台を現代にするとこんな感じるのではないだろうか。何はなくとも周りからジロジロ観察されたりするのはまさしく今のアフリカ社会である。
本書の最後の方にはこうした記述がある。
「行く前は、私の人生を変えるくらいの重大な出来事だと思っていたが、帰ってみたら「そんなこともあった」くらいのことになっていた」
「英語がペラペラになったわけでもなく、とっても楽しいことがあったわけでもない」
「そこで暮らしたことは私の人生に何の影響も及ぼしていない気がするけれどホテルに泊まって汚い格好でニンジンを丸かじりする生活は、なかなかよかった」
現状のままの生活を続けた場合、何となくであるが本書のこの記述そのままに私の2年間は終わるような気がする。
巻末の岸本葉子氏の解説でも書かれているがこのエッセイは普通の人の普通の行動パターンで成り立っている。そうしたところからみても「協力隊員として途上国に行けば何かがある」という幻想を抱いている人がこれを読むと大半の協力隊員の活動・生活の結果を疑似的に体験できるのではないかという気がした。